現在のデジタル社会において、私たちの生活はITシステムなしには成り立ちません。ウェブサイト、スマートフォンアプリ、クラウドサービス、そして
スマート家電まで、ありとあらゆるものがインターネットに接続され、私たちの生活を便利にしています。しかし、その便利さの裏側には常に「脆弱性(ぜいじゃくせい)」という見過ごせないリスクが潜んでいるのをご存知でしょうか?

脆弱性とは何か?見過ごされがちなシステムの問題点
脆弱性とは、セキュリティ上の弱点、問題点、または欠陥のことを指します。これは、システムの設計・開発段階で意図せず生じてしまうものから、新しい技術の登場や攻撃手法の変化によって後から発見されるものまで多岐にわたります。
例えば、Webアプリケーションのコードに誤りがあったり、オペレーティングシステム(OS)に未修正のバグがあったり、ミドルウェアの設定に不備があったりすることも脆弱性です。さらに、近年普及が進むスマートフォンやスマート家電といったIoT機器にも、見過ごされがちな脆弱性が潜んでいることがあります。
では、なぜこのような脆弱性が存在するのでしょうか?その最大の要因は、設計・開発の過程で、開発者が最新のセキュリティ対策への認識が不十分であったり、あるいはリリース後に新たな脆弱性が発見されたりすることにあります。技術は常に進化しており、それに対抗するサイバー攻撃の手法も日々巧妙化しているため、一度安全だと思われたシステムでも、時間の経過とともに新たな脆弱性が見つかることは珍しくありません。
なぜ今、脆弱性診断が不可欠なのか?
こうした脆弱性を放置することは、組織にとって極めて大きなリスクとなります。例えば、以下のような事態が引き起こされる可能性があります。
⚫︎不正アクセスによるシステム乗っ取りや情報漏洩
⚫︎ウェブサイトの改ざんやサービスの停止
⚫︎他のシステムを攻撃するための「踏み台」としての悪用
これらの事態は、企業の信頼失墜、顧客離れ、法的責任、そして多大な経済的損失に直結します。そのため、業種や企業規模に関わらず、すべての組織にとって脆弱性診断は不可欠なセキュリティ対策と言えるのです。
脆弱性診断とは、IT資産(Webアプリケーション・サーバー・ネットワーク機器など)に潜む「脆弱性」がないかを確認し、調査することです。その目的は、サイバー攻撃から組織を守り、潜在的なリスクを事前に把握することにあります。
脆弱性診断の主なターゲット
脆弱性診断は、システムの様々なレイヤーに対して実施されます。ここでは、主な診断対象をご紹介します。
1. Webアプリケーション診断
多くの企業が運営するウェブサイトは、顧客との接点であり、同時に悪意のある攻撃者にとって情報窃取のターゲットとなりやすい場所です。ウェブアプリケーション診断では、インターネット上に公開されているサービスに対するセキュリティリスクを詳細にチェックし、例えばSQLインジェクションやクロスサイトスクリプティングといった脆弱性がないかを確認します。
2. クラウド診断
近年、クラウドサービスの利用は企業活動に不可欠となっています。クラウドは「常に最新の環境でアクセスできる」というメリットがある一方で、適切な設定がされていないとセキュリティリスクが格段に高まる恐れがあります。クラウド診断では、ユーザー側のクラウド環境に潜む設定ミスやアクセス権限の問題を発見します。例えば、「誰でもアクセスできる可能性のある設定ミスがないか」「不要な権限が付与されていないか」などを詳細に調査し、クラウド環境の安全性を確保します。
3. スマートフォンアプリ診断
現在のビジネスにおいて、スマートフォンアプリの利用は欠かせません。スマートフォンアプリ診断は、アプリ自体に潜む弱点や、ユーザーデータの保護対策が適切に施されているかを確認します。例えば、個人情報の不適切な取り扱い、通信経路の暗号化の不備、認証機構の脆弱性などがないかを検証し、ユーザーが安心してアプリを利用できる環境を構築します。
4. プラットフォーム/ネットワーク診断
プラットフォーム診断は、サーバーやネットワーク機器などに対して行われる脆弱性診断です。具体的には、ファイアウォール、ロードバランサ、仮想化インフラ、サーバーOS(ゲストOS)、サーバーミドルウェア、VPNなどが診断対象となります。ネットワークスキャンを用いたり、各機器の設定を詳細に確認したりすることで、システム基盤全体の脆弱性を検知します。
脆弱性診断:システムの「健康診断」を行うタイミングと頻度
人間の健康診断で「今年は異常がなかったから、一生健康でいられる」ということはないように、あなたのシステムも同じです。脆弱性診断は、一度行えば終わりではなく、継続的かつ不可欠なプロセスです。どれほど強固なセキュリティ対策を講じていても、サイバー攻撃者は常に新たな弱点を探し、攻撃を仕掛けてきます。
定期的な診断は、潜在的な脆弱性を早期に発見し、対処するための「ワクチン」のようなものです。これにより、リスクや損害を大幅に軽減できます。では、いつ、どのくらいの頻度で実施すべきでしょうか? 社内のガイドラインが最良の指針となりますが、少なくとも年に1回、または大規模なバージョンアップや新機能の展開時に行うのが「黄金律」です。
脆弱性診断:システムの「健康診断」を行う
タイミングと頻度
人間の健康診断で「今年は異常がなかったから、一生健康でいられる」ということはないように、あなたのシステムも同じです。脆弱性診断は、一度行えば終わりではなく、継続的かつ不可欠なプロセスです。どれほど強固なセキュリティ対策を講じていても、サイバー攻撃者は常に新たな弱点を探し、攻撃を仕掛けてきます。
定期的な診断は、潜在的な脆弱性を早期に発見し、対処するための「ワクチン」のようなものです。これにより、リスクや損害を大幅に軽減できます。では、いつ、どのくらいの頻度で実施すべきでしょうか? 社内のガイドラインが最良の指針となりますが、少なくとも年に1回、または大規模なバージョンアップや新機能の展開時に行うのが「黄金律」です。
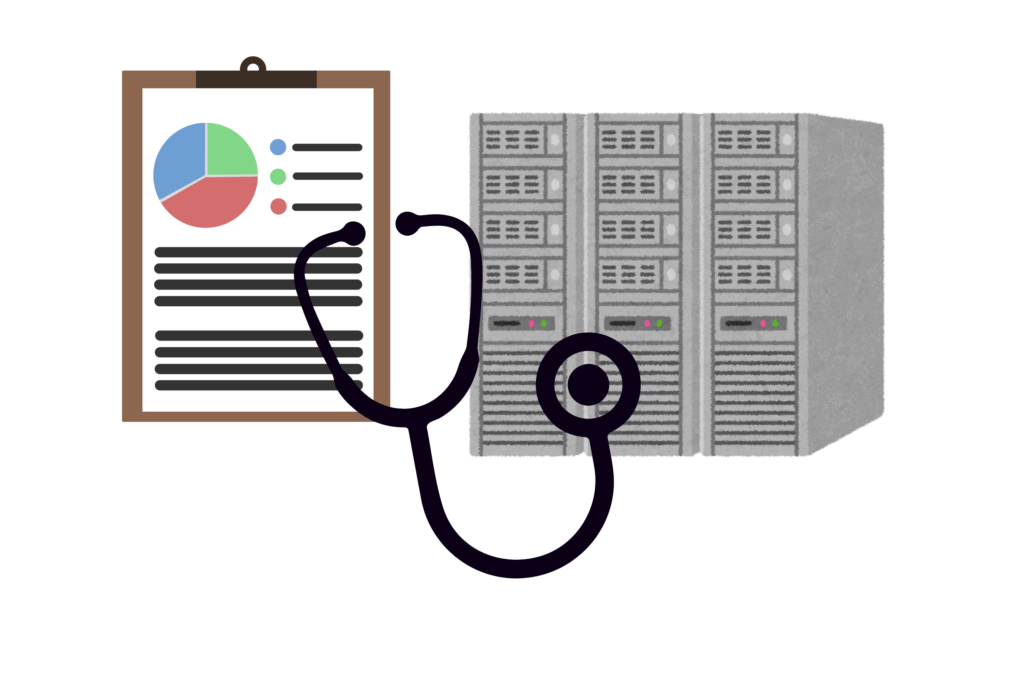
脆弱性診断(セキュリティ診断)の流れ
1. 事前ヒアリングによる要件整理
診断に先立ち、お客様とのヒアリングを通じて、診断対象となるシステムの概要、目的、スコープ、利用環境などを丁寧に整理します。
システムの種別(Webアプリ、クラウド、モバイルなど)や診断の目的(法令遵守、取引要請、内部統制など)、利用環境(本番環境/検証環境)、認証要件、想定されるリスクなどを明確にし、診断プランの最適化を図ります。
この段階での情報整理が、効果的かつ無駄のない診断につながる重要なステップとなります。
2. 診断準備:環境整備とスケジュール調整
次に、実際の診断を円滑に進めるための準備を行います。診断対象の環境が適切に整備されているか、使用するツールとの互換性に問題がないかを確認した上で、診断スケジュールを確定します。
また、診断中に不要なブロックや誤検知を避けるため、ファイアウォールやWAFなどの通信制御機能については、必要に応じて一時的な設定調整も行います。業務への影響を最小限に抑えるための体制づくりも、この段階で整えていきます。
3. 脆弱性診断の実施:自動+手動のハイブリッド方式
診断は、弊社独自のツールを用いた自動診断と、セキュリティエンジニアによる手動診断を組み合わせたハイブリッド方式で実施されます。
さらに、アクセス制御の不備や不要な情報公開の有無、モバイルアプリにおける暗号化方式や通信の保護状態なども含めて、幅広く診断を行います。診断結果はすべてログとして記録され、次のフェーズへと活かされます。
4. 診断結果の分析とレポート作成
診断によって得られたデータをもとに、発見された脆弱性を分析し、それぞれのリスクレベルや対応の優先度を整理した上で、最終レポートを作成します。
レポートには、脆弱性の一覧、深刻度の評価(High/Medium/Low)、攻撃シナリオ、発生しうる被害例、そして具体的な対応策を記載します。
また、対象読者に応じて内容を調整し、経営層には全体リスクと対応方針を、開発・運用担当者には技術的な詳細と実践的な修正案を分かりやすく提供します。
診断後のサポート
ご要望に応じて、脆弱性の修正後に再診断(リテスト)を行うことで、対策の有効性を確認し、より安心いただけるセキュリティ体制の構築を支援いたします。
「情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」登録済
当社が提供する「ベトテルサイバーセキュリティ脆弱性診断サービス」は、経済産業省が策定する「情報セキュリティサービス基準」に準拠したサービスとして正式に認定されており、「情報セキュリティサービス台帳」にも登録されています。
- サービス名:ベトテルサイバーセキュリティ脆弱性診断サービス
- 登録番号:025-0007-60
